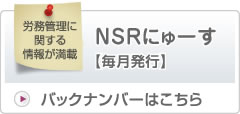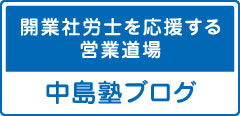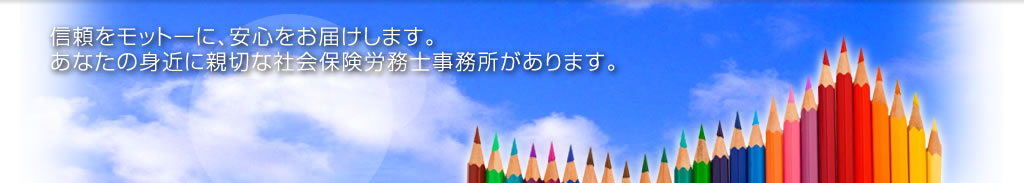
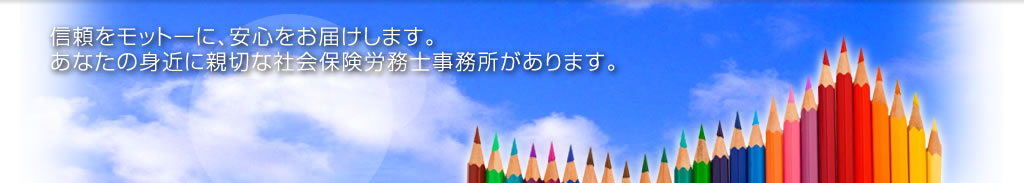
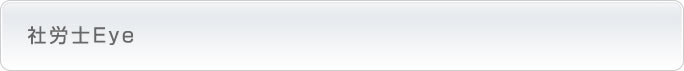
モデル就業規則について(厚生労働省)
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
モデル就業規則 (平成25年4月1日)
○WORD版
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/model.doc
○PDF版
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/model.pdf
モデル就業規則(東京労働局)
就業規則の作成例
※以下の作成例に載っている規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
【全体版】
○就業規則の作成例(全体・PDF版)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0137/7265/201471092827.pdf
○就業規則の作成例(全体・Word版)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0137/7266/20147109298.doc
就業規則作成の手引き(東京都 TOKYOはたらくネット)
はじめに
使用者には、労働者が自己の能力を最大限に発揮し、心身ともに健康的に働き続けられる職場環境を整備する責務があります。
労働者にとって魅力ある職場を作ることは、使用者にとっても、人材の確保及び育成という観点から極めて有利です。
そのためには、労働条件や人事・服務規律などの職場のルールを明らかにして、労使双方がその内容をよく理解していることが大切です。
この職場のルールを明文化したものを就業規則といいますが、就業規則を作成することによって、労使の権利義務関係が明らかになり、互いにこのルールを守ることによって、無用なトラブルの発生を防ぐことができます。
労働基準法では、使用者の義務として「この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、…(中略)…労働者に周知させなければならない」(第106条)、すなわち、使用者は、労働基準法をはじめとする労働関係諸法令を理解したうえで、従業員に周知するよう示しています。
しかしながら、労働法の趣旨をよく理解し、これを誠実に守っている使用者は、決して多いとは言えないのが実態です。
そこで東京都では、初めて就業規則を作成される使用者を対象に、就業規則の作成にあたって必要な労働法を基礎から学んでいただき、従業員の誰もが理解しやすい就業規則を作成していただくために本冊子を作成しました。会社の実情にあった就業規則を作成していただき、よりよい労使関係の構築に役立てていただければ幸いです。
最後に、労働相談情報センターでは、労働に関する各種資料の提供及び労働条件や労使関係など労働問題全般に関するご相談を受け付けています。どうぞお気軽にご利用ください。
平成23年3月
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
全文ダウンロードはこちらから (46.4MB)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/shugyokisoku_all.pdf
トラック運送事業のためのわかりやすいモデル就業規則2014
http://www.miyatokyo.or.jp/pdf/20140516a.pdf
東京オフィス
東京都新宿区市谷田町1-19-2 ECS第19ビル3階
TEL:03-6280-7156